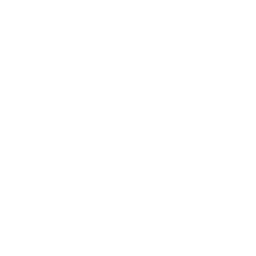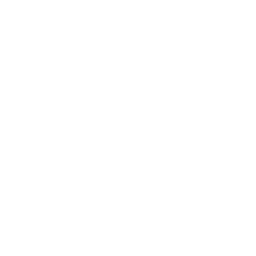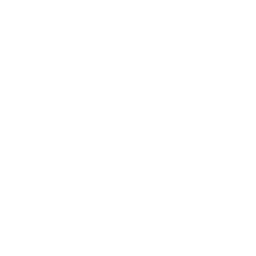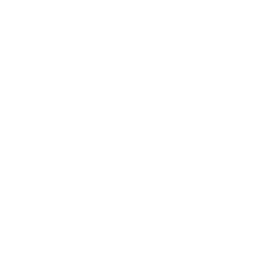膝
・オスグッド・シュラッター病
・半月板損傷
・膝蓋腱炎・膝蓋大腿靱帯炎(ジャンパー膝)
・変形性膝関節症
関連記事

膝がポキポキ鳴る原因をご存じですか?
私は10歳位の時から35歳位までの間、よく膝がポキポキと鳴っていました。現在ではほとんど鳴らなくなったのですが、子供の頃はなぜ音がするのか疑問を感じていました。今回は、膝の音に関して見ていきたいと思います。 音の種類に注意しましょう 音の鳴り方にも種類があります。ここでは音の種類とその内容について見ていきましょう。 ①ポキッ・パキッ 膝関節内の関節液が膝の動きによって圧力変化を受け、気泡が生じて弾けることがあります。この現象は生理的なものであり、痛みがなければ心配はいりません。 ②コリッ・コリコリ 足の動きの中で、靭帯や腱が骨に引っかかって外れる際に音がすることがあります。これはよくある現象で、痛みがない限り問題ありません。 ③ゴリッ・ガクッ 半月板損傷や靭帯損傷で起こります。関節内に引っかかりがあると、膝の曲げ伸ばしのたびに音や違和感、痛みを感じることがあります。 ④ミシミシ・ゴリゴリ この音は軟骨が擦れ合っている可能性があり、変形性膝関節症の初期症状であることが多く、痛みや腫れを伴うこともあります。 上記①~④のうち、③と④は治療が必要です。 治療の目安 膝の音…

変形性膝関節症の対処法とは
膝の痛みを感じる方は、主に中高年に見られます。朝起きあがる時、椅子や床から立ちあがる時、階段を降りる時など、日常の動作で膝に痛みを感じるようになります。変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)は、関節にある軟骨がすり減ったり、骨と骨がこすれて変性することで、炎症や痛みなどがでる病気です。 痛みと変形の原因 膝関節の表面は軟骨で覆われています。変形性膝関節症では、加齢や内反膝(O脚)、肥満などが原因となり関節の軟骨が摩耗(すり減る)します。その軟骨のかけらが、関節の内側を覆う滑膜を刺激することで炎症が生じます。その結果、膝の屈伸動作による痛みが発生したり、関節内に水がたまったりします。 ひざの変形は、軟骨が摩耗た結果、骨どうしがぶつかり合うことで進行していきます。大腿骨(だいたいこつ)と脛骨(けいこつ)が直にぶつかり続けると、互いの骨をすり減らしていき、やがて骨が変性し、骨棘(こつきょく)という骨のとげができます。骨棘の形成が進行すると、膝の変形も進行します。 変形性膝関節症になりやすい人 〇肥満気味の方〇内反膝の方〇40代以降の方〇女性〇膝に負担がかかる仕事…

「膝のお皿の下が痛い!」それは膝蓋腱炎(ジャンパー膝)かもしれません。
膝蓋腱炎は20歳以下の活発にスポーツをやっている方に多くみられる症状ですが、つい先日50代の私が膝蓋腱炎になってしまいました。スクワットが原因でした。膝の屈伸時や階段を下る際に強めの痛みを感じました。すぐにスクワットをやめたので短期間で治りました。今回はその膝蓋腱炎(ジャンパー膝)についてお話し致します。 膝蓋腱炎とは 膝蓋腱炎とは、スポーツ時のジャンプや着地、ダッシュやストップなど、急激な動作を繰り返すことによって、膝蓋腱に炎症が発生するスポーツ障害です。男性に多いのが特徴で、中学~高校にかけて発症する事が多い傾向にあります。また、膝蓋骨(膝のお皿)の上が痛くなることもあり、これを膝蓋大腿靱帯炎(しつがいだいたいじんたいえん)といい、ひとくくりにジャンパー膝と呼びます。 スポーツ以外でも、膝の屈伸動作が多い職業や、登山などでも発症します。 膝蓋腱炎がみられるスポーツ・・・バレーボール、バスケットボール、サッカー、陸上、野球など 好発年齢・・・12歳~20歳(10代の男性が多い) 原因 膝蓋腱炎は、ジャンプや着地の繰り返しによって膝蓋腱に過度な負荷がかかることで発生し…

ランナー膝(腸脛靭帯炎)~膝の外側が痛い!
ランナー膝(腸脛靭帯炎)は、膝の外側が痛くなるスポーツ障害です。マラソンなどの長距離ランナーでよく発症することから、通称「ランナー膝」と呼ばれていますが、自転車競技でも多く見られます。 ランナー膝のメカニズム 膝の外側の骨のでっぱり(大腿骨外側上顆)を、膝の曲げ伸ばしによって腸脛靭帯が前後に通過します。この際の摩擦により炎症が起きます。腸脛靭帯は膝を伸ばした状態では大腿骨外側上顆の前にありますが、膝を曲げていくとそれを越えていき、30度ほど曲げると大腿骨外側上顆の後ろに位置します。この30度屈曲位付近で摩擦が生じます。もちろん日常生活の歩行等では問題は起こりませんが、マラソンなどの繰り返しの膝運動(オーバーユース)による摩擦により炎症が起こります。 ランナー膝の主な原因と症状 原因となるもの 〇陸上競技(主に長距離)、自転車、バスケットボール、バレーボールなど〇偏平足、O脚(内反膝)〇ランニング初心者〇足の筋力が弱い方〇足の筋肉が硬い方〇その他、硬い路面や下り坂での練習、休養不足など 症状 腸脛靭帯炎の主な症状は、膝の外側に感じる痛みです。初期の段階では、運動後や長時…
オスグッド・シュラッター病
【原因・症状】
オスグッド・シュラッター(Osgood-Schlatter)病は、アメリカの医師Osgoodとドイツの医師Schlatterによって報告されたため、オスグッド病やシュラッター病と呼ばれることもありますが、正式にはオスグッド・シュラッター(Osgood-Schlatter)病と呼ばれています。
成長期の脛骨近位端に生じる骨端症であり、脛骨結節に限局した痛みと腫れ、脛骨結節の触診時の痛みを特徴とします。10歳から15歳の年齢層が最も多く発症します。
成長期では、膝関節を構成する大腿骨と脛骨の成長軟骨が成熟する過程で、長軸が伸びるため、大腿四頭筋の伸長が追い付かず、相対的に筋と、筋と骨をつなぐ腱が短縮した状態になります。大腿四頭筋が短縮し骨に対する牽引力がかかりやすくなっている状態で、かつキックやジャンプ動作などによる、強い筋肉の収縮が繰り返されることによって、発育途中の脆弱な脛骨粗面(膝の前面に)負荷がかかることにより起こります。
【治療】
物理療法:低出力超音波治療、電気治療(低周波)、メドマー(加圧マッサージ機)
手技療法:下肢のマッサージ、ストレッチ
鍼灸:膝蓋骨周囲及び大腿部に鍼治療を行います。灸も効果が期待できます。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
その他:ベルトの装着(サポーター)をご提案する場合もあります。
半月板損傷
【原因・症状】
半月板とは、太ももの骨(大腿骨)とスネの骨(脛骨)の間にある軟骨組織です。内側と外側に一つずつ存在し、関節にかかる体重を分散させたり、関節の位置を安定させる役割を担っています。
そんな半月板に、日常生活やスポーツなどで負荷がかかり、傷がついた状態を「半月板損傷」と呼びます。
半月板を損傷すると以下のような症状がみられます。
・膝を曲げたり、伸ばしたりすると、痛みが生じる
・膝の関節が完全に伸びない・曲がらない
・階段の昇降や膝の屈伸などをしていると「ゴキッ」と異常音がする
・歩いているときに「ガクン」と膝が落ちる(膝崩れ現象)
・膝が引っかかって急に動かなくなる(ロッキング)
・膝が腫れる など
【治療】
物理療法:低出力超音波治療、電気治療(低周波、高周波)
手技療法:下肢のマッサージ、ストレッチ
鍼灸:大腿部に鍼治療を行います。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
その他:膝のサポーター装着をご提案する場合もあります。
膝蓋腱炎・膝蓋大腿靱帯炎(ジャンパー膝)
【原因・症状】
膝の皿(膝蓋骨)の下が痛むものが膝蓋腱炎、上が痛むものが膝蓋大腿靱帯炎といいます。これらをひとくくりにジャンパー膝といわれています。
バレーボールやバスケットボール、走高跳やサッカーのゴールキーパーなど、跳躍動作を繰り返す人、あるいはランニングをする人でひざの前の方に痛みが出ている場合は、ジャンパー膝である可能性が高いです。
スポーツのみではなく、仕事などで膝の屈伸動作が多い方、長距離を歩く方などにも発症します。
ジャンパー膝は放っておいて簡単に治ることもありますが、残念ながらなかなか治らずに時間が経過することも少なくありません。症状が改善しない方は治療をお勧めします。
ジャンパー膝の原因は「膝蓋腱・膝蓋大腿靱帯」というスジの中で「血管が余計に増えてしまう」ことだと考えられています。血管が余計に増えてしまう原因は「繰り返しの負担(負荷)」です。
膝の屈伸やジャンプの着地のたびに、膝蓋腱・膝蓋大腿靱帯が引っ張られます。特に強い負担がかかった時には腱の中で小さな傷が生じます。すると、その傷を治すために血管が増えてきます。普通であればこの傷は2週間ほどで治り、傷が治ると増えた血管も消滅するのが通常の流れです。ところが、負担のかかる動作をあまりに繰り返すと、できた傷が治る前に新たに損傷ができてしまい、血管が減る暇がなく増え続けてしまいます。
血管が増えると、それと一緒に神経線維も増えてしまうため、痛みの原因になります。
「痛みが強くなってきた」「なかなか痛みが治まらない」と感じる方は、膝を休ませてあげた方が良いでしょう。
<有効なストレッチ>
大腿四頭筋、腸腰筋のストレッチ
【治療】
物理療法:低出力超音波治療、高出力超音波治療、電気治療
手技療法:大腿部のマッサージ、ストレッチ
鍼灸:膝蓋腱周囲、膝蓋大腿靱帯周囲に鍼治療を行います。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
その他:必要に応じてサポーターのご提案、テーピング等を行います。
変形性膝関節症
【原因・症状】
変形性膝関節症とは、膝の関節が加齢や過度の負荷によってすり減り、痛みや動きの制限を引き起こす疾患です。
主に中高年に見られ、関節内の炎症や関節組織の変性が関与し、末期には骨の変形も引き起こします。
女性では40歳以降、男性では50歳以降の発症が多くなります。また、全体の男女比は1:4と、明らかに女性に発症しやすいことが分かっています。
痛みの原因は、ひざの関節内にある「滑膜(かつまく)」の炎症です。
関節の中は関節液という液体で満たされていますが、炎症は関節液の中を漂う「軟骨のかけら」が関節の内側を覆う滑膜を刺激することで、炎症が生じます。
軟骨の表面は本来非常に滑らかで、こすっても簡単にはすり減りません。しかし、ひざは1日に何千回もこすれます。これが数十年続くと、タイヤがすり減るように徐々に磨耗が進んでいきます。その結果、すべすべしていた軟骨の表面はザラザラと毛羽立ちはじめ、軟骨自体が削り取られていくのです。こうして削り取られた軟骨のかけらが滑膜を刺激して、炎症を引き起こします。
【治療】
物理療法:低出力超音波治療、電気治療(低周波)
手技療法:下肢のマッサージ
鍼灸:関節及び大腿部に鍼治療を行います。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
その他 :ご自宅で簡単にできる筋力トレーニング法をご提案します。