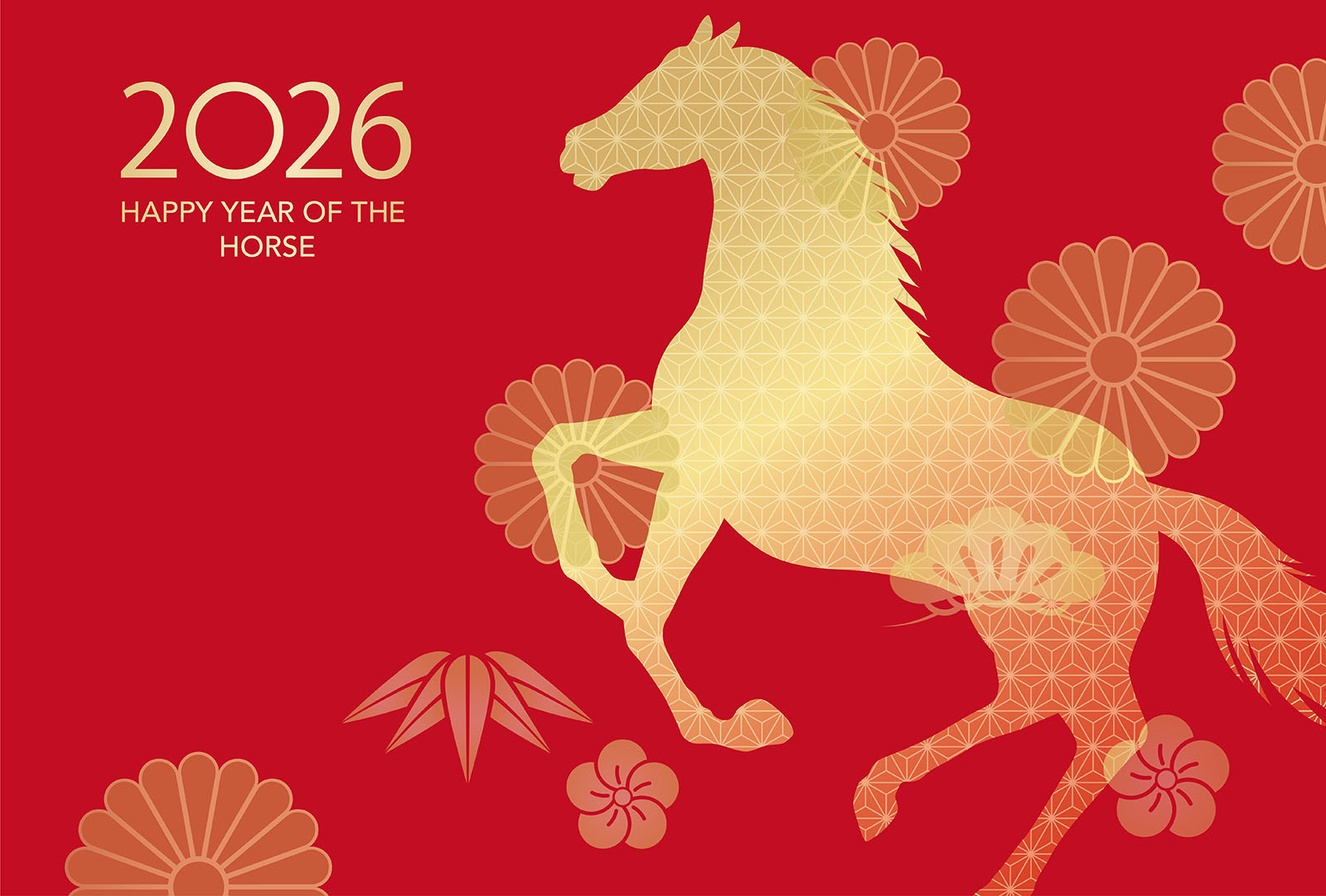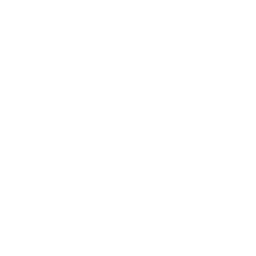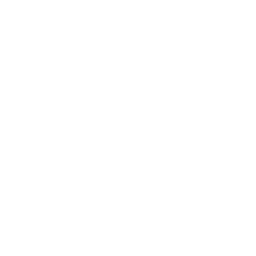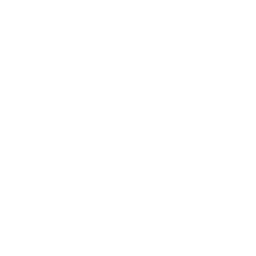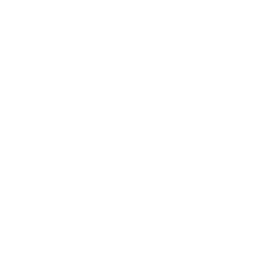肩
・肩関節周囲炎
・腱板損傷・腱板断裂
・インピンジメント症候群
・胸郭出口症候群
・投球障害(野球肩)
関連記事

肩の痛みの軽減やケガの予防に重要なトレーニング法とストレッチについて
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。 今年の第1回目は、昨年最後のブログ「インピンジメント症候群」でお伝えした肩関節のトレーニング等についてお話ししたいと思います。 ローテーターカフ(回旋筋腱版)とは ローテーターカフとは、肩関節を構成する深層の4つの筋肉(インナーマッスル)の総称です。役割としては、肩関節を動かすというより「関節を安定させる事」です。関節がスムーズに動かせるように上腕骨と肩甲骨を引き寄せています。ローテーターカフが弱くなると、関節安定性が失われ、スムーズな関節の運動が出来なくなります。また、ローテーターカフを強化することで、肩のケガに対するリスクを軽減し、肩の痛みを予防し、さらにはスポーツパフォーマンスの向上も期待できます。 ローテーターカフは①棘上筋、②棘下筋、③小円筋、④肩甲下筋で構成されます。それぞれの働きを説明します。 ①棘上筋(きょくじょうきん)・・・腕を横に上げる動作(外転)の開始時に働きます。 ②棘下筋(きょくかきん)・・・腕を外側にひねる動作(外旋)で働きます。 ③小円筋(しょうえんきん)・・・腕を外側にひねる動作(外…

「肩は動かせるのに腕を上げると痛い」それはインピンジメント症候群かもしれません
前回のブログで少し触れました「インピンジメント症候群」について今回はお話ししたいと思います。 インピンジメント症候群とは? インピンジメント(impingement)とは「衝突する」・「挟み込み」という意味です。肩の関節で何かがぶつかり合うことにより痛みや動かしにくさが出る病気です。では何がぶつかっているのでしょうか。それは肩関節の間が狭くなり、肩を構成する上腕骨と肩峰、腱板、滑液包が衝突することにより起こります。 主な原因 インピンジメント症候群の原因はスポーツや仕事、姿勢、加齢などが原因とされています。 スポーツ・仕事 野球やテニス、水泳など、腕を頭上に上げる動作が多いスポーツや、頻繁に重い荷物を持つ作業など、肩に負担がかかる動作を繰り返すことで、肩関節に炎症が起こりやすくなります。 姿勢 猫背などの姿勢が長時間続くと、肩周囲の筋肉が緊張したり硬くなり、筋肉の連携がうまく作用しなくなる事によって関節の動きが悪くなります。これによりインピンジメントを起こしやすくなります。 加齢 40歳以降になると、肩周りの筋肉や腱が自然と衰えてきます。これにより腱板の柔軟性が低下し、不安…

「肩がゴリゴリ鳴る」その原因とは
若い方(10代~20代)で肩が鳴る方もいらっしゃいますし、中高年でいきなりなり始める方もいらっしゃいます。肩の音にはいくつかの原因がありますので、今回はこの音について見ていきましょう。 原因 〇関節内の摩擦音肩関節は骨(肩甲骨、上腕骨、鎖骨)、腱、滑液包、それをとりまく筋肉で構成され、複雑な構造になっています。この中で骨と骨がぶつかったり、腱がこすれることによって音が鳴ることがあります。 〇気泡がはじける音肩関節内の関節液が肩の動きによって圧力変化を受け、気泡が生じて弾けることがあります。この現象は生理的なものであり、痛みがなければ心配はいりません。 〇筋肉が緊張により硬くなっている肩関節に関連する様々な筋肉が、「使い過ぎ」や「こり」、「けが」などにより、緊張したり硬くなると音がすることがあります。 <音が鳴る際に痛みを伴う場合の考えられる疾患> 〇インピンジメント症候群肩の関節にある骨と骨の間が狭くなってしまい、腕を動かすときに肩の腱や筋肉が擦れたり、挟まれたりすることで痛みや炎症を引き起こす病気です。 〇腱板損傷・腱板断裂肩関節の安定性を維持したり、動きを補助・調整…

肩の前が痛い、物を持ち上げられない!それは「上腕二頭筋長頭腱炎」かも知れません。
以前私も上腕二頭筋長頭腱炎になったことがあります。大学生のある時期、腕を鍛えるために毎日ダンベルトレーニングをやっていましたが、ある日肩の前に違和感を感じました。「たいしたことないな」と思いトレーニングを継続したところ、ある日から強い痛みを感じるようになり、じっとしていても熱く焼けるような痛みを感じたり、物を持ち上げるのが辛くなったりしました。しばらく筋トレを休み様子をみていたら、いつの間にか痛みは消えていきました。治るのに3カ月くらいはかかったような記憶があります。その頃は知識がなかったため、トレーニングを継続して悪化させてしまいましたが、途中でやめたのは良い判断だったと思います。もし我慢して継続し続けていたら、さらに悪化して腱が断裂し、手術が必要になったかも知れません。当院にも上腕二頭筋長頭腱炎の治療をする方がいらっしゃいます。腕や肩をあまり使わないよう皆様にお伝えるのですが、昨年痛みを我慢してテニスを継続された方(60代男性)が、腱の断裂をおこしてしまいました。その後3カ月間は大好きなテニスも出来なくなり、安静を余儀なくされていました。肩に痛みを感じたら、まず休ませてください。…
肩関節周囲炎
【原因・症状】
・肩関節周囲炎は、肩関節周囲の組織が炎症を起こした状態で、肩関節の周囲にある腱や粘液包、靭帯などの組織に炎症や圧迫が生じることで引き起こされます。
・肩の痛みや運動制限、時には肩関節の可動域の減少などの症状を引き起こすことがあります。
・40代~50代によく見られるだけで、30代、60代、70代でも起こります。
肩関節周囲炎の主な原因としては、以下のような要因が挙げられます。
・過度の使用や急激な運動:肩を過度に使ったり、急激な動きをしたりすることで、肩関節周囲の組織に負担がかかり、炎症が起こることがあります。
・肩の姿勢や使い方の問題:姿勢の悪化や無理な肩の使い方によって、肩関節周囲の組織に負担がかかり、炎症が生じることがあります。
・外傷:肩関節または上腕に直接的な外力が加わった場合、肩関節周囲炎を引き起こすことがあります。
・年齢と共に進行する変化:加齢によって、肩関節周囲の組織に変化(変性)が生じ、炎症が起こることがあります。
肩関節周囲炎の治療には、安静、物理療法、抗炎症薬の使用、運動療法などが用いられます。
【治療】
物理療法:電気治療、超音波治療を肩関節に直接行います。
手技療法:肩甲骨周囲の筋肉にアプローチします。
運動療法:急性期(炎症期)を過ぎたら(痛みはじめてから1~2か月後)関節の可動域に合わせて運動を行います。また、ご自宅で出来るストレッチなども提案して行きます。
鍼灸:急性期には関節周囲の筋緊張に対し可動域制限の進行を抑えます。拘縮期(痛みはじめてから1~2か月後)には運動鍼(鍼を打ちながら動かす)を行うことがあります。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
腱板損傷・腱板断裂
【原因・症状】
・腱板損傷や腱板断裂は、肩の腱板(Rotator Cuff)に生じる損傷です。
・腱板とは、肩関節の安定性や運動の円滑性を保つために重要なインナーマッスル(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)とそれにつながる腱です。
・腱板損傷は、急激な外傷や長期間の過度な使用、スポーツ、加齢による変性などが原因で発生することがあります。
・症状として、肩の痛み、運動制限などがあります。診断は、症状の詳細な評価や画像検査(MRI、エコー検査)によって行われます。また、治療方法は、軽度の場合は保守的治療(安静、物理療法、抗炎症薬の使用)から手術治療までさまざまです。
【治療】
物理療法:超音波治療、電気治療(中周波、低周波)
手技療法:肩関節周囲の筋緊張へのアプローチ、運動療法
ご自宅で出来るインナーマッスルの強化法及び柔軟性を取り戻すためのエクササイズの提案。
鍼灸:腱板及びその周囲の筋肉に対して緊張を軽減させる目的で行います。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
インピンジメント症候群
【原因・症状】
・インピンジメント症候群は、腕を上げた際、上腕骨の一部が烏口肩峰アーチを通過する際、腱板や粘液包が肩峰と衝突し痛みや炎症を起こす症状です。
・この症候群は、肩の使い過ぎ(オーバーユース)、スポーツや職業での繰り返し動作、加齢による変性などが原因となります。
主な症状
・腕を上げたときの痛み(寝ている時に痛む場合もあります)
・肩の可動域の減少
・肩の筋力低下
・持続的な違和感や炎症
診断方法
・問診と視診:患者の症状の詳細な確認と肩の動作を評価。
・理学検査:インピンジメントテスト(ホーキンス・ケネディテスト、ニーアーテストなど)を実施。
予防方法
・運動前に肩の柔軟性を高めるためのウオーミングアップを行う。
・肩に負担をかけない動作を心掛ける。
・肩周りの筋力を強化し、安定性を向上させる。
インピンジメント症候群は、早期に適切な治療を受けることで症状の改善が期待できます。肩の痛みが続く場合は、専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
【治療】
物理療法:超音波治療、電気治療(中周波)
手技療法:関節周囲の筋緊張を和らげるマッサージ。症状によってストレッチや運動療法。また、インナーマッスル強化法のエクササイズをご指導します。
鍼灸:急性期には消炎作用、鎮痛作用を目的とした鍼治療を行い、時期をみて可動域を広げる鍼治療を行います。
また、この症状は休息と安静が必要です。肩の使い過ぎや痛みの出る動作は避けましょう。
胸郭出口症候群
【原因・症状】
・胸郭出口症候群とは、腕神経叢と鎖骨下動脈が①前斜角筋と中斜角筋の間、②鎖骨と第一肋骨の間、③小胸筋の肩甲骨烏口突起停止部の後方を走行しますが、①~③の部位で締め付けられたり、圧迫されたりして起こる疾患です。それぞれ①斜角筋症候群、②肋鎖症候群、③小胸筋症候群と呼ばれ、総称して胸郭出口症候群と言われます。
・症状として、腕の痺れや肩甲骨周囲の痛み、握力低下、上肢の冷えや浮腫みが生じます。
・原因は多岐にわたりますが筋肉の緊張や姿勢なども影響を与えます。
【治療】
物理療法:電気治療(低周波)、超音波治療
手技療法:首、上背部の筋緊張を和らげた後、肩甲骨の運動療法を行います。また、姿勢を管理する手法などアドバイス致します。
鍼灸:胸郭出口周囲の筋肉に針を打ち、パルス電流を流します。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)
投球障害(野球肩)
【原因・症状】
野球やバレーボールなどの投球動作、肩を酷使するスポーツ選手に多く見られる肩の障害です。長期間にわたり肩関節を酷使することにより関節や筋肉、腱に過度な負担がかかり、痛みや機能障害が生じます。
・肩峰下滑液包炎(けんぽうかかつえきほうえん):肩の滑液包に炎症が起こり、痛みを伴います。
・回旋筋腱板損傷(かいせんきんけんばんそんしょう):肩の回旋筋腱板(ローテーターカフ)が損傷し、痛みや可動域の制限が生じます。
・上腕二頭筋長頭腱炎(じょうわんにとうきんちょうとうけんえん):上腕二頭筋の腱に炎症が起こり、痛みが生じます。
原因としては、肩の酷使、投球フォームの不良、肩関節周囲筋肉群のバランス不良等です。
予防法として、まず休養です。ついでインナーマッスルの強化、投球フォーム等の改善などが挙げられますが、プレー前のウオームアップやプレー後のクールダウンも重要です。
【治療】
物理療法:電気治療(中周波)、超音波治療、低出力超音波治療
手技療法:関節周囲の筋肉へのアプローチ、運動療法
鍼灸:腱板や周囲筋肉へ鍼治療を行います。消炎作用や筋肉を和らげる効果が期待できます。また、試合前(練習前)の鍼治療は非常に効果的です。(鍼治療は患者様と相談のうえ決定します。)